2011年8月6日(土)から14日(日)まで、大阪・山陰方面へ旅行に行きました。
今年の夏休みの予定を悩んでいたら、両親から萩・津和野に旅行に行くからと誘われ、世界遺産になった石見銀山もセットで、山陰方面へ家族旅行に行くことにしました。さらに、プレ旅行で、2004年3月の日根荘旅行(鳥取旅行)では、時間がなかったために行けなかった日根荘の七宝滝寺と、大阪府立弥生文化博物館、国立民族学博物館に行ってきました。
最後になりましたが、旅行準備や旅行中などでお世話になった方に、お礼を申し上げます。
| 8月6日(土) | 夜行バス 池袋豊島区役所前2235→0650(0830)なんば周辺 |
| 8月7日(日) | JR難波駅→(JR関西本線)→天王寺駅→(JR阪和線)→信太山駅→(徒歩)→【池上曽根遺跡】・【弥生文化博物館】→(徒歩)→信太山駅→(JR阪和線)→日根野駅→(徒歩)→【歴史館いずみさの】→(徒歩)→日根野駅→(JR阪和線)→信太山駅→(徒歩)→【弥生文化博物館】→(徒歩)→信太山駅→(JR阪和線)→日根野駅→(バス)→犬鳴山BS→(徒歩)→犬鳴山グランドホテル紀泉閣 |
| 8月8日(月) | 犬鳴山グランドホテル紀泉閣→(徒歩)→【犬鳴山七宝滝寺】→(送迎バス)→日根野駅→【民族学博物館】→【ゆかり】(お好み焼き屋)→【だるま】(串カツ屋)→夜行バス |
| 8月9日(火) | 松江駅→【松江城】→【出雲立つ風土記の丘】→【加茂岩倉遺跡】→【荒神谷遺跡】→【出雲大社】→【温泉津】(龍御前神社、温泉津港)→旅館のがわや |
| 8月10日(水) | 温泉津→【沖泊】、【鞆ヶ浦】→【石見銀山】(羅漢寺、大久保長安墓、豊栄神社、清水谷精錬所跡、清水寺、新切間歩、吉岡出雲墓、福神山間歩、龍源寺間歩、栃畑谷・昆布山谷、佐毘売山神社、石見銀山街道、西本寺山門、観世音寺)→ゆうひパーク浜田→萩本陣 |
| 8月11日(木) | 萩本陣→【松陰神社周辺】→【東光寺】→【吉田松陰の墓】→【菊屋住宅】→【田中義一生家跡】→【高杉晋作誕生の地】→【円政寺】→【青木周弼の旧宅】→【木戸孝允生家】→【堀内地区】→【萩城趾】→【萩城下】→萩本陣 |
| 8月12日(金) | 萩本陣→【津和野】→津和野駅1520→(SL)→1646湯田温泉駅→湯田温泉 ホテル松政 |
| 8月13日(土) | ホテル松政→湯田温泉駅0902→(JRスーパーおき2号)→1144大田市駅→(バス)→世界遺産センター→【石見銀山】大久保間歩ツアー(大久保間歩、釜屋間歩)→大田市駅→(JR山陰本線)→出雲市駅→夜行バス 出雲市駅北口ロータリー1910→0830新宿駅西口 |
| 8月14日(日) |
今年の夏は、山陰旅行。9日に出雲で両親と合流するまで一人旅。
午前中に部活をして、夜は池袋でキャラメルボックスを観劇。そのまま、池袋の豊島区役所前から夜行バスへ。集合場所に係の人はいないし、出発時間を過ぎてからバスが来るし、かなりドキドキ。原宿で大阪行きに乗り換える。最近の格安夜行バスってこんなシステムなんだなぁ…。途中、3回の休憩でも、目が覚めてしまうのも歳なのかなぁ。さらに、8:30到着予定なのに、6:50に到着。時間をつぶしてからだね。
![]()
なんば駅周辺で、時間をつぶしてから、JRで信太山駅へ。
 |
信太山駅から、大阪府立弥生文化博物館までは、道路の色が違う。アスファルト色の舗装ではなく、茶色く舗装されているので、迷子にならず安心。 |
   |
| まず、隣の池上曽根遺跡から見学。公園化されていて、定期的にフリーマーケットをやっているのにビックリ。復元された建造物が充実していてよかったよ。情報館のおじちゃんが、荷物を預かってくれたので、見学しやすかったし。 |
| 池上曽根遺跡 大阪市和泉市池上町から泉大津市曽根町にかけて広がる池上曽根遺跡は、南北1.5km、東西0.6km、総面積60万平方メートルと全国屈指の規模を持つ弥生時代の集落跡。集落の周囲が大きな溝で囲まれていたことから、環濠集落と呼ばれる。弥生時代の前期から後期(紀元前3世紀~紀元後3世紀)にわたって営まれ、中期(2200年~2000年前)にもっとも栄えた。 「解説板」より |
|||
 |
 |
 |
池上曽根遺跡では、巨大な建物と井戸を中心とする「祭祀(まつり)の場」や、ものづくりに関わる各種の「生産の場」が集落の中心部で営まれていた。重要な「まつりの場」を取り巻くように「生産の場」が設けられていたことから、ものづくりが特別に扱われたいたことがわかる。 |
 |
 |
 |
80畳の大きさを誇る高床建物(いずみの高殿)と、その南側の直径2.3mのクスノキをくりぬいた巨大な井戸(やよいの大井戸)。周囲にはていねいに石器や土器が埋められ、ここで様々な祭祀(まつり)が行なわれていたことがわかった。「まつりの場」の遺構は正方位に合わせて築かれ、中国からの影響が見受けられた。 「まつりの場」に接して鉄器、青銅器、石器などを作っていた工房が「生産の場」として設けられていた。「まつりの場」と「生産の場」は立柱と溝で分けられていた。「生産の場」には作業所としての小さな建物が建てられていたが、住居はなく、自然の浅い谷により、住まいと工房も区分けされていた。 |
 |
 |
博物館でも、きれいなお姉さんが荷物を預かってくれた。展示は複製が多かったけど、近畿の弥生時代をすっきりまとめてあったり、映像資料が特に充実していた。特別展は銅鐸。これも近畿中心の展示だったので、明後日行く予定の加茂岩倉遺跡の銅鐸の解説も欲しかったな。
行ってから分かったことだけど、特別展のセミナーで歴博の春成秀爾さんが、銅鐸絵画の話をするってことなんだけど、14時からなのでかなり時間がある。でも、16時までなので、それまでいたら、歴史館いずみさのに行けないばかりか、ホテルの送迎バスにも間に合わない。一瞬の判断で、日根野の歴史館いずみさのに行って戻ってくることにした。受付のお姉さんに、「再入場できるか」って聞いたら、「できる」って教えてくれただけでなく、「荷物も預かりっぱなしでいい」って言ってくれた。超感謝。
身軽になって、日根野へ。しかし、駅からどんなに歩いても、歴史館いずみさのに着かない。駅に戻って地図を見て、また行ってもたどり着かず。結局、電話をしてどうにかたどり着いた。展示は、前に来たときとほとんど変わっていないけど、パンフレットを買ってきました。
で、弥生文化博物館に戻って、春成さんの講演を聞く。『歴博』などの文章を読んでいても感じるけど、話をうまく持っていって断定する感じが面白い。たまに、俺がホントかなぁって感じることも、断定しちゃうおもしろさだな。
本日のお宿「犬鳴山グランドホテル紀泉閣」






何で、犬鳴山なんてところに泊まっているのか、次の日記で
![]()
宿では、ひょっとして外国人だと思われているかも…。犬鳴山のハイキング案内図をもらったら、なぜかハングル入りのものをくれた。もっとちゃんとした日本語に地図もあったのに…。
今日が月曜日で、弥生文化博物館も歴史館いずみさのもお休みだから、昨日はハードスケジュールだった。民博は、月曜やっているので、今日行くことができた。と計画していたら、松江や出雲の博物館は、火曜が休館のところが多い。明日行くのに~ってことで、電話してみたら、夏休みだから開館しているところもあった。
今日も、ハードだった。6時に起きて温泉へ。7時から朝食。8時過ぎにチェックアウト。犬鳴山に行って、10時の送迎バスで日根野駅に戻ってきました。
プレ山陰旅行は、犬鳴山七宝滝寺を見るのが目的。九条政基がほめまくり、雨乞いでは、滝に不浄なものを入れると脅されるところ。前回は、大木までしか行けず、ここまで奥に行く時間がなかったので、今回リベンジでした。気分は、ハイキングなんだけど、結界が張られ、所々に不動さんがいたりして、雰囲気十分。50分歩いて七宝滝寺に到着。本堂の裏に行者の滝があり、鎖で途中まで上ったりするんだろうなぁ。その手前にも滝があるんだけど、売店のおじさんに聞いても、どちらの滝に投げ込むのわからなかった。気になるなぁ。帰りも、うっとうしい虫を散らしながら下山。送迎バスに間に合いました。
|
『政基公旅引付』甲巻 文亀元(1501)年7月20日条に、滝宮での請雨の儀の様子が具体的に記されている。 「20日丙申 晴 簡単にまとめると、滝宮で請雨が行なわれ、もし三日の間に雨が降らなければ、七宝滝で行ない、ついで七宝滝寺不動明王堂で雨乞いを行ない、それでも降らない場合は、七宝滝寺の滝壷に動物の死骸などの不浄の物を投げ入れ龍神を怒らせて雨を降らせるとしている。その結果、どうなったかというと、 「21日丁酉 晴 「22日戊戌 霽(はれ) 「23日己亥 晴」「24日庚子 天、曇。降雨に及ばず」「25日辛丑 晴」「26日 壬寅 晴」「27日癸卯 霽。夕方、曇」 22日にちょっと降っただけで、27日までずっと晴れていたことが分かります。ところが、28日になると、 「28日甲辰 ということで、無事に雨が降りました。雨が降らないと、旱魃になってしまい文亀4(1504)年2月16日の巫女とその息子が殺されてしまうような事件が起こってしまうわけです。 「13日己未 晴 日記から、盛大にお祭りを行なったことが伝わってきます。 このほかにも、『政基公旅引付』には、犬鳴山や七宝滝寺は、以下のように出てきています。 政基が日根荘に来たばかりの文亀元年5月2日の記事 文亀元年6月14日の記事 まだまだありますが、この辺で…。 |
 |
 |
犬鳴山の入り口 霊域として、結界が張られています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
川に沿って道が上っていきます。岩場を抜けたり、川によって岩が削られていたり、滝があったり。完全に、参拝モードではなく、ハイキングモードで山登り。 |
 |
 |
 |
金高橋を渡り、歩いて行くと山道の先に、瑞龍門が見えてきます。 |
 |
 |
 |
(左)虚空蔵菩薩殿 (中)霊光殿 (右)護摩場 |
 |
発達繁昌の守護 神明大権現について 神明大権現は、徳川上代の当山中興、見滝上人が寛文10(1670)年当山晋住にあたり、本尊不動明王に奉告勤行のため、本堂へ向かわれる途中現在の霊地にさしかかったとき、黒竜白竜二竜王の昇天の奇瑞を拝せられた。上人いたく感激されてこの黒白二竜王を当山の御法神として神明大権現の御神号を呈し奉り祭祀せられた。爾来発達繁昌を念ずる参拝者の香煙の絶えることがなかった。 |
 |
 |
(左)出世稲荷大明神 (右)九頭竜大神 |
 |
 |
地蔵菩薩建立の辞 夫れ幽玄にして神秘なるは神意なる乎。余去る七月塔の滝に於て地蔵菩薩安産するを拝したり。茲に於て信徒と計り菩薩の再出現を願い新たに石像一躰を建立し天力地蔵菩薩として此處に安置し奉る。 昭和三十五年十二月二十四日 天光教会 三宅神清 敬白 |
 |
 |
(左)岩屋不動 (右)お亀石 |
 |
宇多天皇寛平2(890)年3年15日、紀伊国の猟夫、当山の行場である蛇腹附近に鹿を追ったとき、樹間に大蛇あり。猟夫を呑まんとす。猟夫その由を知らず。愛犬しきりに鳴いて猟を遮ぎぬ。猟夫怒りて愛犬を切る。愛犬の首飛んで大蛇に咬みつき共に斃る。猟夫我が生命を守りし義犬を弔わんが為に剃髪して、庵を結んで余生をおくりたりと。その事朝聞に達し、一乗山改め、犬鳴山と勅号を賜った。 (解説板より) |
 |
志津の涙水 昔、淡路の小聖という者しばしば御所へ出入りしていたが、官女の志津女という美人に想われる身となった。小聖は修業の妨げとふり切って犬鳴山中へのがれて来た。志津女は修行僧を思い切れず跡を追い、諸国を探し求めたのであるが、遂に泉州犬鳴山で小聖が修行しているとのことを風のたよりに聞き、修行僧に一目逢うべく犬鳴山まで来たがけわしき渓谷と山路、それに飢えを寒さ、なお俄かに白雲がたちこめて来て道を見失い遂に路傍に悶死したのである。 村人は、志津女の死体を懇ろに葬り、供養されたのであった。こうした事があってから犬鳴山に白雲が立ちこめる日は必ず雨が降るので、村人は志津の涙雨と云い、又、倒れていた附近からこんこんと清水が湧き出ている処からこの水を志津の涙水と以後よぶようになった。一心をこめた願い事がある場合、この水を持ち帰り毎日飲用すると必ずや願い事が成就するとのことである。 (解説板より) |
 |
 |
(左)身代わり不動明王 (右)ボケよけ不動尊 犬鳴不動明王は、古来より事故や災難から身を守り難病平癒命乞不動明王として尊信せられ、殊に本尊大竜不動明王は、福徳開運、願望成就の守護として霊験まことにあらたかな明王として信仰されています。 ボケ除け不動尊の拝み方 |
 |
 |
 |
| 日記には、「本堂の裏に行者の滝があり、鎖で途中まで上ったりするんだろうなぁ。その手前にも滝があるんだけど、売店のおじさんに聞いても、どちらの滝に投げ込むのわからなかった。気になるなぁ。」って書きました。 左の写真が、手前の滝です。なんか、「穢れた物」を投げ込みやすそうですよね。でも、中と右の写真の行者の滝の方が、鎖があって上る修行をするようになっているなど、ありがたみがありそうな滝なので、こっちに投げ込むのかなぁ? |
||
 |
行者くぐり岩 行者尊の台座岩穴をくぐることにより行者さまの偉神力と御尊像胎内に納められたる心経の功徳力と穴の地下にうずめられたる近畿三十六不動尊霊場のお砂すみの功力により穴をくぐる人々が六根清浄となりもろもろのけがれ不浄がなくなり所願成就の法益を受けることができます。 くぐる時は、 摩詞般若波羅密多 三辺 南無神変大菩薩 三辺 唱えて礼拝し次に六根清浄と唱えつつ三回穴をくぐり下さい。 |
 |
 |
 |
 |
 |
道の途中に、不動三十六童子がいました。 第一番 矜羯羅童子(上左) 第四番 光網勝童子(上中) 第五番 無垢光童子(上右) 第六番 計子爾童子(中左) 第七番 智慧憧童子(中右) 第九番 召請光童子(下左) 第十四番 師子光童子(下右) |
 |
 |
| 日根野から梅田まで行くには、天王寺で地下鉄に乗り換えるんだけど、そのまま大阪に行っても同じなんだね。JR大阪と地下鉄・阪急の梅田の駅が同じって、訳わからない。何はともあれ、バス・ターミナルを見つけ、ロッカーに荷物を預け、千里の民族学博物館へ。 太陽の塔を見て、民博友の会に入っているから入場料は無料。新しくなったオセアニアの展示では、小学生に混じってクイズに参加。普段、いかに展示を流して見ているのか実感。クイズのために、改めてしっかり見ると、おもしろいって思う一方で、全部の展示をあんなに集中してみたら、死んでしまうだろうな。集中して見なくても、疲れてしまうほどの展示物の量。全体のパンフがないのもよくわかった。正直、盛りだくさんすぎて、ポイントを絞って見たいものを見に来ないと、何の収穫もないまま終わってしまうかも。ゆっくり、閉館まで時間をつぶすつもりだったのに、3時にはギブアップ。ボーッとさせてくれない展示の迫力に負けてしまったね。 |
 |
 |
 |
民族学博物館で、いっぱいいっぱいになって梅田に戻り、ガイドブックで見つけたお好み焼きの「ゆかり」へ。そばとかいろいろ入った広島風もお腹にたまるけど、シンプルな大阪風のお好み焼きもいいね。 |  |
 |
| さらに、新世界の「だるま」って串カツ屋へ。串カツって、行列までして食べるものか疑問だけど、せっかくだから、行列に参加。お好み焼きをしっかり食べているから、おまかせ串セットは食べられないので頼まずに、小さい生ビールとハモ串、一般的な串3本とづけマグロ串を食べて終了。並んだかいのあるおいしい夕食でした。 その後、梅田に戻り、バスターミナルのタリーズで日記を書き、夜行バスで松江へ。大阪から松江の夜行バスは、JRのくにびきなので、3列シートの豪華版。学生のノリのOLさんのおしゃべりがうるさいの気になったけど。そういえば、満席だった東京から大阪のバスも、ドタキャンで隣が空席になり、広々使えたし、帰りの出雲から東京のバスはガラガラだったので、窮屈な思いをしないですんだ。でも、年取ったのかバタンキュウで寝られなかったり、上手く寝る姿勢をつくれずに首を寝違えたり、あんまりしっくりできなかった。 |
 |
 |
 |
![]()
行き当たりばっ旅、全開。夜行バスで着いて何もなく、風土記の丘も9時からだから、どこか行こうと思いついたら、美保関へ。しかし、バスの中で、ガイドブックを見たら、思ったより遠い上に、バスターミナルで乗り換えて、さらに歩かないと着かないから、時間がかかりすぎると思い、途中下車。松江城を見て、駅に向かって、風土記の丘へ。
って、書いていると、何となくうまくいっているみたいだけど、これを大荷物を持って移動しているし、バスは一方通行で路線はわかりづらいし、かなりドタバタのハードな行動でした。せめて、まずは、荷物をロッカーに入れてから動けばいいのにね。でも、松江城を外だけでも見ることができたし、予定はこなせたからよしとしよう。
| 松江藩主は、堀尾三代、京極一代、松平十代である。松平家初代の直政公は、富国・安民・質素・節財等の大綱を示し、藩政の基礎を固めた。 慶長19年(1614)大坂冬の陣に際し、母・月照院は、14歳で初陣する直政に対し「君は徳川家康の孫で、父結城秀康は名将である。父に劣らぬ奮戦をせよ」と励まし、馬印(隊旗)を縫って与える。越前隊と加賀隊が先を争って真田丸に進むが、弓銃が激しく撤退する。その時、一将が進み出る。見れば直政である。従士の天方通総は馬を止め矢表に立ち「大将が先がけるとは何事ぞ」と諫めるが直政はさらに進む。通総は再び矢表に立ち塞がる。何度も矢表を争う主従を見た城将・真田幸村は、直政の勇気と従士の忠義を賞し、弓銃を撃たせず、主従の武士道の誠を讃え、櫓より軍扇を投げ与える。 この美談徳目は、時代を越えて輝き、郷土の先人は感嘆し銅像建立へと進んだ。明治から大正にかけて小銅像を製作され、昭和2年に米原雲海作の直政公初陣像が松江城本丸に建立される。昭和18年戦時により供出される。 その後、再建の気運が高まり、昭和52年、松平直政公銅像再建委員会が設置され、平成20年、同建設委員会が設置される。銅像製作は、二科会理事の倉澤實氏による。 (松平直政公銅像建設委員会・松江市 設置 解説板より) |
 |
 |
| 岸清一先生は、慶応3年7月4日、松江雑賀町(現在の松江市雑賀町)で出生されました。 明治、大正、昭和にわたり、わが国法曹界の第一人者として活躍される一方、日本体育協会会長、国際オリンピック委員会委員として、日本スポーツ界の育成と、その国際的地位の向上に半生を捧げられ、「近代スポーツの父」として敬慕されています。 先生は、スポーツ振興等のためにしばしば巨額の浄財を投じられましたが、日本スポーツ界の拠点とも言える、現在の「岸記念体育館」も先生の遺志によって建築されたことは、私たちのよく知るところです。 また、愛郷心豊かな先生は育英事業をはじめとして、郷土のために数々の功績を残されました。 こうした岸清一先生の偉業を讃えるとともに、遺徳を末永く後世に伝えるため、この銅像が建てられました。 (解説板より) |
 |
 |
 |
松江の町の写真 (左)竹島資料室の写真 |
で、松江のメインは、出雲立つ風土記の丘。資料館自体は、ありきたりで目新しいものはなかったけど、出雲の災害をまとめた特別展は、すっきりまとめられていて、興味深かった。さらに、それ以上に、周辺一帯をひっくるめた遺跡がおもしろかった。学習館で、鍵と懐中電灯を借りて、公園内の岡田山一号墳へ。鍵を開けて、横穴式石室に入れたのは、いい経験をできた。さらに、石室がむき出しになっている岩屋後古墳へ。石舞台に比べれば、さすがに小さいけど、迫力があったよ。その後は、バスの本数が少なく、待ち時間が長くなってしまって、日焼けするしかなかったけど…。
 |
箱式石棺 箱式石棺は、板状の石材を箱形に組んだ棺で、古墳時代の一般的なお墓の一種です。この箱式石棺は、大橋川に面した東津田町石屋の丘陵尾根上で発見され、発見時には人骨の一部が残っていました。 |
| 古墳時代の住まい この家屋は、古墳時代の建物を推定復元したものです。 |
 |
 |
奈良時代の住まい(掘立柱建物) この家屋は、渋山池遺跡(東出雲町)で発見された建物跡をモデルに、奈良時代の一般的な住居を推定復元したものです。発掘調査では、地面に残された痕跡しかわかりませんが、その上屋を、推理を交えて復元してみました。 |
| 岡田山二号墳 ここに築かれている岡田山二号墳は、直径約43m、高さ約6.5mの円墳で、出雲地方としては松江市大垣町の大塚古墳に次ぐ大きな円墳である。 |
 |
 |
岡田山一号墳 ここにある古墳は、前方後方形に築造された岡田山一号墳である。昭和45年度に復元整備工事が行なわれているが、全長24m、後方部の幅14m、その高さは4mある。復元工事の際に、中段の葺石に沿って円筒埴輪がめぐらされていることなどがわかった。 閉塞石(下) 岡田山一号墳の入り口をふさぐために用いられた石材。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 石室の入口で記念撮影 |
 学習館で借りた懐中電灯 |
岡田山一号墳の横穴式石室 銘文入円頭大刀や、内行花文鏡、馬具など優れた副葬品がこの石室内から発見され、梅原末治博士の報文(大正12年)により、その出土位置をほぼ知ることができる。 |
 |
 |
 |
 |
岩屋後古墳 意宇平野の南西隅、丘麓の水田中に位置するこの古墳は、県下最大規模の石棺式石室を内部主体にもつものである。古墳の墳形は不明だが、20m前後の規模と推測される、石室は、羨道部・前室部・奥室部に分かれるが、後世の破壊により現在は奥室のみ遺存している。羨道部の壁を割石で積むのに対して前室・奥室の壁はいずれも一枚の切石で構成する。特に奥室天井石は内外面ともに平入り四洋式の家型に加工し、出雲東部を中心に分布する石棺式石室の典型例として注目できる。 |
|
松江駅に戻り、喫茶店で一休みして、出雲空港へ両親を迎えに行き、レンタカーで家族旅行開始。って言っても、自分で作った計画だから、好き勝手に連れ回しただけって感じもするけど。
まずは、銅鐸で有名な加茂岩倉遺跡へ。何でこんなところにって感じの山奥。農道を通そうって考えなければ、絶対見つからなかっただろうな。火曜日で、遺跡ガイダンスがお休みだったけど。さらに、銅剣で有名な荒神谷遺跡へ。ここの資料館は、夏休みなので定休日でも開館。どちらの遺跡も、発掘した状態を復元していて、わかりやすかったけど、交通の便が悪く、レンタカーがないと苦しいね。
| ★荒神谷遺跡 この史跡は、1984(昭和59)年、農道予定地の発掘調査で全国最多の銅剣358本が出土、翌年に隣接地で銅矛16本、銅鐸6個が出土し、日本古代史上最大の発見として大きな脚光を浴びた遺跡である。これら弥生時代の青銅器群が埋納されていたのは、仏経山(『出雲国風土記』記載の神名火山)から延びる山間の小さな谷斜面で、現在は発見当時の状況が再現されている。 |
荒神谷遺跡発掘再現 1984(昭和59)年、このあたりに新しく広域農道を建設する計画がありました。遺跡があるかどうか、それを確かめるために予定のところどころを掘ることにしました。7月11日発掘開始、2日目に小さな銅片がみつかりました。「青銅器だろうか」「まさか」と発掘関係者は思いました。しかし、そこから銅剣358本が発見されたのです。このときの発掘調査はひとまず9月に終わりました。 |
|
 |
 |
銅剣発掘再現-1984年8月の状況 穴のなかに4列に並べて埋めた銅剣が見つかりました。左から34本、111本、120本、93本、合計358本です。右の銅鐸や銅鐸と同じく、銅に錫を加えた合金の青銅を材料としたものです。ただし、製作当初は、このように青い色ではなく、金と銀の中間のような光り輝く色でした。銅剣は、本来は短い柄をつけた短剣で、突き刺す武器です。それが弥生時代の日本では扁平な大型品になり、祭りの道具に使われるようになります。この銅剣も、祭りの道具で、柄もつけなかったものでしょう、刃を研いですり減った痕跡もありません。ここでは、銅剣の出土した地面の上30cmほど土を盛って発掘当時の地表面を再現し、そこに青銅製の複製品を出土した状況で置いてみました。 (左上)最初に発見された銅剣358本の複製 |
 |
 |
|
それから、出雲大社に向かったけど、案の定、時間が足りなくなり、出雲そばで昼食、なんて計画は、企画倒れ。そういえば、今回の旅行では、昼食は、悲惨だったかも。7日の昼食は、日根野駅前のコンビニで買ったおむすび。8日は、昼食・夕食セットのつもりでお好み焼き。結果として、夕食で串カツも食べたんだけどね。9日は、昼食抜き。10日は、石見銀山で、定食のご飯がなくなってしまい、おそばだけ。11日は、ちゃんと、「あじろ」の定食を食べられた。12日も、「能濃」のうずめ飯定食に、その前に「沙羅の木」の昭和50年生まれのコーヒーゼリーも食べたな。でも、13日は、湯田温泉駅で買ってもらったおむすびで済ませてしまったし。かなり貧しい昼食生活だったかな。
話はそれてしまったけど、出雲では、古代出雲歴史博物館へ。出雲大社のいろんな展示と、加茂岩倉・荒神谷の銅剣・銅矛・銅鐸など国宝がどっさり持ってこられている。出雲がしっかりまとめられている展示でした。
出雲大社では、本殿の屋根の葺き替えなどの大改修中。で、大国主命が、御仮殿の拝殿に仮住まい。そのために、工事現場の中に入れてもらって、茅葺を間近に見たり、貴重な体験ができた。短パンじゃダメってことで、駐車場まで、着替えに行ったり、バタバタしたけど。
 |
 |
★出雲大社 出雲大社御本殿大屋根特別拝観 出雲大社「平成の大遷宮」のため、本殿は素屋根に覆われていました。素屋根内の階段を上り、本殿を上から拝観することが出来ました。 (左上)本殿の仮殿 |
 |
(左下)末社十九社 大國主大神が「むすびの神」(人々の幸福を生み成しおきすきになる神の意)である事から旧暦十月には、全国の神々が出雲大社にお集まりになって、人々の幸福発展のために神議なさる神事が行なわれます。この御社は、その時の神々のお宿で平素は神々の遙拝するところです。現在でも、出雲では旧暦十月を神在月と申しますが、他地方では神無月と申し、前後には、出雲へ神々をお送りします「神送り」、出雲からのお帰りを迎える「神迎え」の行事が行なわれます。 |
|
| その後、一路、温泉津へ。温泉津の町は、夏の夜神楽のために、自主的に一方通行にしたり、ちょっと面白かった。「旅館のがわや」も古くよき時代のお宿。着いてすぐ、夕食前に、お父さんと龍御前神社と温泉津港までお散歩。リアス海岸の谷間に無理矢理つくった町なのがよくわかった。神社なんて、崖から生えているから。夜は、夜神楽の公開練習を見にお散歩。切った竹にロウソクを入れて明かりにしたり、幻想的だった。 |  |
| 温泉津 銀の積み出しは、始めは、大内氏の支配が及んでいた鞆ヶ浦で行なわれていたが、銀山の支配が毛利氏に移ると温泉津湾にある沖泊を積み出し港とした。さらに、1672(寛文12)年に河村瑞賢によって西回り航路が開発されると船の寄港地となり、廻船業を主とする問屋は20余軒にも達した。 毛利氏が、銀山の領有を狙って出雲の尼子氏と戦うため、温泉津に軍事的な拠点を置いたのが、弘治元(1555)年。毛利元就は、伊藤重佐を湯主に任命。5年後の永禄3(1560)年には、輝元が、重佐の孫に当たる信重に、温泉役(入浴税)と地銭(宅地税)を納付するように申しつけた記録が残る。関ヶ原の戦いの後、徳川の世に移ってからも、伊藤家は代々、湯主を務め、温泉役を納めたが、地銭については、慶長10(1605)年、初代銀山奉行の大久保長安により、永代免除の措置がとられている。岩見銀の積み出し港であり、物資搬入の基地でもあったので、銀山を支える外港の基盤強化・発展促進を図っての優遇策だったと考えられる。 |
(左)温泉津港 (右)内藤家庄屋屋敷 |
|
 |
 |
|
本日のお宿「旅館のがわや」






 |
「旅館のがわや」の石風呂 |
 |
 |
 |
夜の温泉津の町 竹の明かりが幻想的ですね。 |
 |
泉薬湯 温泉津温泉元湯の由来 伊藤家温泉屋文書は、「中世室町時代に伊藤重佐という者が、温泉場を開発した。温泉場の開発は、村の草創である」と伝えている。 (解説板より) (上)看板の上の狸 |
 |
|
 |
![]()
| 8月10日(水) 翌朝は、早起きして、薬師湯へ。日本温泉協会の評価がオール5。超熱いお風呂で、出たり入ったりを繰り返すのがいいみたい。気持ちいい、ってより、慌ただしい温泉だった。 「旅館のがわや」の朝食 |
 |
| 薬師湯 番台後方の階段を上がると、踊り場には、アンティークな椅子や照明器具が置かれ、2階の半円形の空間には、洋風のくつろぎの場がある。さらに、屋上に出てみると、白いテーブルと椅子があり、セルフサービスのコーヒーが飲めるよう心配りがなされている。 |
 |
その後、沖泊、鞆ヶ浦と、石見銀山の積み出し港を見に行く。今はもう、ひなびた漁港。昔の賑わいは、想像できない。鼻ぐり岩は、満潮だったからかあまり見れず残念。でも、こんなところまでつきあってくれた両親に感謝。
それから、石見銀山へ。ガイドブックには、パーク&ライドで、世界遺産センターに車を置き、大森の町まで、バスで行くようになっている。混んでいて、センターの駐車場にも車を置けなかったらどうしようと心配だったけど、宿の仲居さんから、平日は全然大丈夫で、空いていたら、代官所跡や銀山公園の駐車場にも、止められるって教えてもらった。実際に、着いたときは、がらがらでちょっと拍子抜け。帰るときは、大森の駐車場は満杯になっていたり、土曜日に再訪したときは、センターの駐車場も、満杯で、想像していたような光景だったけど。
まずは、銀山公園の駐車場に車を置いて、無料ガイドの時間まで、五百羅漢を見に行った。戻ってきてから、龍源寺間歩の無料ガイドツアーに参加。ガイドさんが言っていたけど、石見銀山は、わかりにくい世界遺産。見ただけでわかるものは少なく、説明してもらったりして意味づけしないと、ただ間歩を通っておしまいって感じになってしまうんだろうな。他人のペースに合わせながらのツアーはちょっと大変だけど、それ以上のものが得られたと思う。
龍源寺間歩のガイドツアーは、コースを歩くのが前提で、大久保長安、吉岡出雲、宗岡佐渡のお墓や豊栄神社、佐毘売山神社、清水寺には寄らなかったのは、残念。勝手に、吉岡出雲のお墓を見に山を登ったりしたけど、その間の説明を聞けないから、バランスが難しいな。でも、ガイドなしだと、わからないし、ペースもつくれないだろうし。
間歩に入るときも、写真を撮ったりしていて、中でも説明を聞けず、お母さんにはあきれられちゃったけど、中はひんやり。しかし、重機のない中世にあれだけのものを掘るのはすごいな。一日3cmとかしか掘れないってのも納得。
大森の町に戻ってからは、家族で行動。自分のペースで、観世音寺に寄り道したり、寄り道している両親より先に勝手に行ったり、自分勝手全開の見学でした。さらに、丁銀パンを買って、代官所跡の資料館へ。代官所って造りではなく、明治になってからの郡役所だから、秩父事件の役所って感じ。豪商だった熊谷家住宅で、この旅行最大の事件が発生。見学し終わり、車を取りにいったら、足に違和感が。熊谷家住宅を出るときに、靴が履きにくく足がむくんだかなって思ったけど、やっぱり違和感。よく見たら、同じニューバランスの茶色の靴だけど、ヒモの結び方が違って、脱いでみたらサイズも違う。結局、履き間違えたってことなんだけど、急いで銀山公園の駐車場から、車を代官所の駐車場に移し、お母さんに預け、熊谷家住宅に戻ると、俺の靴がよけられていて、受付のおばちゃんがちょうど連絡中で、本当の持ち主の女性が来てくれた。平謝りするしかなかったけど、早く気がついて良かった。
| ★石見銀山 博多の商人神屋寿禎が1526(大永6)年に銀山開発を始めた。1533(天文2)年、灰吹法を導入し銀の生産量は一気に高まった。 |
 |
 |
羅漢寺(五百羅漢) |
 |
 |
 |
大久保石見守墓 大久保石見守は、名を初め「藤十郎」といい、のち「長安」と改めた。甲州(山梨県)にいた関係で、鉱山に明るい長安は、慶長5(1600)年秋、徳川家康の命令で、石見銀山へ派遣された。翌6年、長安は、石見国9万7800石の初代奉行に就任、其れまでの銀山発掘を竪堀りから坑道堀り(横堀り)に改めた。数多くの坑道堀の中で、釜屋間歩を掘り当てて、3600貫(13.5トン)の運上銀(上納銀)を産出して石見銀山の最盛期をつくった。 慶長7(1602)年7月、長安は、石見守に任じられ、従五位下の叙されて俸禄は2万石となった。その後、佐渡、伊豆、院内などの金銀山の奉行も兼務した。 (掲示板より) |
| 豊栄神社 ご祭神は、戦国時代、石見銀山を14年間領有した安芸国(広島県)郡山城主元就である。 (掲示板より) |
 |
|
 |
 |
|
| 清水寺山門 元神宮寺(佐毘売山神社の別当寺)の山門であったが、昭和6(1931)年3月に清水寺と合併し移築したものである。 (掲示板より) |
 |
 |
| ★間歩とは 江戸時代の、採掘操業の「山」、坑道を「間歩」と呼んでいた。 石見銀山の間歩(坑道)は、元禄4(1691)年には92か所でしたが、文政6(1823)年の古文書によると、新旧あわせて279か所とされ、最近の現地調査では、空気抜きなどを合わせると、500か所を超える坑道を確認しています。 |
 |
 |
新切間歩 新切間歩は、幕府代官所直営の「御直山」と呼んだ間歩の一つで、正徳5(1715)年、代官鈴木八右衛門のときに開発し、最初は疎水坑(水抜き坑)として掘ったもののようである。 (掲示板より) |
 |
 |
 |
| 吉岡出雲墓 戦国時代、毛利家の銀山付役人だった吉岡隼人は慶長5(1600)年11月、徳川家康の命令で石見に下った代官頭大久保十兵衛長安に切米100俵で召し抱えられ、銀山の採掘を担当することになった。 (掲示板より) (左)お墓 (中)そばにある間歩 (右)作業場の跡? |
||
 |
 |
福神山間歩 この間歩(坑道)は、採掘にあたった山師個人が経営した「自分山」のものですが、一時期、代官川崎市之進のころには、代官直営の「御直山」の坑道にあった。「御直山」は、天保15(1844)年には、23か所まで増えるが、「自分山」は、享保14(1730)年に55か所もあったものが、天保15年には9か所となってしまう。石見銀山には、主な鉱脈が32本あったと伝えられており、そこから岩盤の亀裂に沿って30cm前後の幅で鉱石を含んだ支脈が延びていました。 (解説板より) |
 |
栃畑谷・昆布山谷 参道から佐毘売山神社に向かって左側の谷が出土谷、右側の谷が昆布山谷で、龍源寺間歩出口前の川に沿ったこの谷一帯が栃畑谷である。どの谷も銀山開発に伴って造成した平坦地が階段状に連なり、石垣や井戸、間歩(坑道)が見つかっている。 |
 |
 |
佐毘売山神社 この祭神は、鉱山の守り神である金山彦神で、別名では「山神社」といい、鉱夫や村人からは「山神さん」と呼ばれ親しまれていた。 |
 |
 |
 |
石見銀山街道(鞆ヶ浦道) 山吹城跡を通って、鞆ヶ浦に抜けます。 |
 |
 |
下河原吹屋跡 江戸時代初期、ここで銀の製錬が行われていた。 |
| 西本寺山門 西本寺は元西本坊と称し、江戸時代初期の寛永年間に銀山の熊谷宗右衛門尉直政の請により六世空乗の代に出雲国神門郡白枝村から現在地に移転したと伝わる浄土真宗本願寺派の寺院である。 |
 |
 |
石見銀山代官所地役人遺宅 渡辺家 この建物は、代官所の銀山方役所に勤務する銀山附地役人坂本氏の居宅であった。 |
| 自動販売機 周りの風景にマッチしています。 |
 |
 |
石見銀山御料郷宿泉屋遺宅 金森家 江戸時代、石見銀山附御料150余村は支配上6組に分けられていた。18世紀の中頃には、大森には六軒の郷宿が設けられ、公用で出かける村役人等の指定宿として、また代官所から村方への法令伝達等の郷用を請け負っていた。文献から、泉屋の主人川北氏は文化7(1810)年まで「波積組(主として現在の江津市の一部)」の郷宿を務めたことが知られている。 |
| 石見銀山代官所地役人遺宅 三宅家 建物は、代官所の銀山方役所に勤務する銀山附地役人田邊氏の居宅であった。 |
 |
 |
 |
 |
| 観世音寺 岩山の上にあり、江戸時代には大森代官所が銀山隆盛を祈願するための祈願寺だった。本堂のほか山門と鐘楼が残されている。 (左)下から見上げた観世音寺 (中)観世音寺から見下ろした風景 (右)観世音寺から見渡した大森の町 |
||
 |
義肢・装具・人口乳房で有名な「中村ブレイス(株)」 2010年メセナ(企業の行なう社会貢献活動)大賞部門に選ばれた。古い空き家を改修して社宅等に活用し、店舗にも貸与して町並み保存に努め、また石見銀山の資料館を開設するなど世界遺産登録に尽力した。海外の子どもの受け入れや石見銀山文化賞の創設など、石見銀山の地域の文化を支え、その魅力を高めたことが評価された。 |
| 石見銀山 中村製パン所「丁銀パン」 |
 |
ゆうひパーク浜田に寄ったりしながら、萩に到着。「萩本陣」の湯めぐりも面白かったよ。夕食のデザートのキウイの載ったゴマプリン。キウイのすっぱ甘さとゴマの苦みが上手くマッチしていておいしかったよ。
| ★ゆうひパーク浜田 | ||
 |
 |
 |
| ★本日のお宿「萩本陣」の夕食 食前酒 季節のサワー |
    |
   |
![]()
この日は、今回の旅行唯一の連泊。荷物は宿に置いておけるし、チェックインの時間も気にしないでいいから、楽だよね。まっ、両親の萩・津和野旅行に便乗して、石見銀山やSLを追加した上に、プレ旅行で、大阪に行くんだから、慌ただしいのは、当然だけどね。
俺は、一日萩を見学予定。両親は、萩焼体験。
まず、宿の近くの松陰神社周辺を散策。明治維新の人材を大量に出した松下村塾。明治政府を支えた伊藤博文の旧宅と別邸。松下村塾の生みの親の玉木文之進の旧宅。ここのガイドのおばちゃんが話し好きで、松下村塾の概略や場所の変遷などを教えてくれた。その後、萩焼屋さんの通りを抜けて、毛利家奇数代の藩主の菩提寺である東光寺。さらに、吉田松陰らの墓所も見てきた。山登りも含めて、けっこう歩いたかな。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下村塾 松下村塾は、吉田松陰が実家の小屋を改修して教室としたものである。名称の由来は、はじめ松陰の叔父玉木文之進がここからほど遠くない自宅に塾を開いて名付けたもので、ついで伯父久保五郎左衛門(松陰の養母の義兄)の久保塾がその名を継いだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
(上左)松下村塾の建物 (上中)松下村塾前で (上右)松下村塾の講義室 (下左)講義室のアップ (下中)幽囚室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田松陰幽囚の旧宅 この旧宅は、安政2(1855)年から数年の間、吉田松陰が幽囚された家で、東側にある3畳半の1室が幽囚室である。もともと、4畳半あったものを神棚が作られてこのようになった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
吉田稔麿誕生の地 吉田稔麿は、天保12(1841)年、足軽の長男としてこの地に生まれた。松下村塾に入門し、高杉晋作らとともに、松陰門下の四天王といわれた。松陰の死後、尊王攘夷運動に参加し、屠勇隊(有志の部隊)を組織した。 |
 |
 |
伊藤博文旧宅 この建物は、最初、水井武兵衛(伊藤直右衛門)の居宅であったが、安政元(1854)年に博文の父十蔵が一家をあげて伊藤家に入家してからは、博文の居宅となった。ここで、博文は吉田松陰の門下に入って教育を受け、志士として活躍した。明治元(1868)年に兵庫県知事に赴任するまでここを本拠とした。 伊藤博文別邸 別邸は、伊藤博文公が明治40(1907)年に東京府下荏原郡大井村に建てたもので、車寄せを持つ玄関の奥に、中庭をはさんで向かって右に西洋館、左に書院を配し、さらにその奥に離れ座敷、台所及び蔵を備えた広大なものであった。当地へは往時の面影をよく残す玄関、大広間、離れ座敷の3棟を移築した。明治時代の宮大工伊藤万作の手によるもので、大広間の鏡天井や離れ座敷の節天井など意匠に優れている。 |
 |
長州ファイブ 文久3(1863)年、イギリスに密航留学した長州出身の5人の若者たち-伊藤俊輔(博文)・井上聞多(馨)・山尾庸三・野村弥吉(井上勝)・遠藤謹助-。近年は、留学先の英国でも彼らの功績が評価され、「長州ファイブ」の呼び名で顕彰されている(ロンドン大学において長州ファイブ
(Choshu Five) として顕彰碑が建てられている)。 |
|
 |
 |
 |
玉木文之進旧宅 玉木文之進(1810~76)は、吉田松陰の叔父にあたり、杉家から出て玉木家(大組40石)を継いだ。生まれつき学識に優れ、松陰の教育にも大きな影響を与えたほか、付近の児童を集め教授し、松下村塾と名付けた。この塾の名称は後に久保五郎左衛門が継ぎ、安政2(1855)年には松陰が継承して、名を天下にあげるに至ったことから、この旧宅は、松下村塾発祥の地といえる。 |
| 東光寺 | |
 |
東光寺総門 護国山東光寺は、元禄4(1691)年、3代藩主毛利吉就が萩出身の名僧慧極を開山として創建した全国有数の黄檗宗の寺院である。 |
 |
 東光寺解脱門 |
 |
東光寺鐘楼 鐘楼の建築年代は、元禄7(1694)年に、4代藩主毛利吉広によって梵鐘が寄進されているので、そのとき同時に建立されたと思われる。 |
 |
東光寺大雄宝殿 大雄宝殿は、元禄11(1698)年、4代藩主毛利吉広によって建立されたものである。建物面積289.61平方メートルの一重裳階付きの仏殿形式で、正面一間通りは吹き放ちになっている、屋根は入母屋造り本瓦葺きで、棟中央の宝珠と両端に鯱を置いている。堂内の土間は漆喰叩仕上げで、建物中央部に格子天井を張るなど黄檗宗建築の姿をとっているが、細部を見ると一般的な唐様の手法が見られる。 |
| 萩藩主毛利家墓所【東光寺墓所】 東光寺墓所は、3代藩主毛利吉就から11代斉元までの奇数代の5藩主と夫人および一族、関係者の墓40基などがあり、総面積5179.55㎡である。墓の周囲には玉垣16か所、神道碑6基、鳥居5基、石燈籠500数基、参道の石畳などの石造物が墓所入口の小門内にある。また、門外には放生池と、それに架かる石橋、維新殉難者の墓などがある。 墓所配置図(墓所左側より-写真は上より)
|
  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
5代吉元&品姫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
9代斉房&幸姫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
3代吉就&亀姫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
11代斉元&由美姫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
7代重就&登代姫 |
 |
 |
 |
| 吉田松陰の墓ならびに墓所 吉田松陰の墓は、表に「松陰二十一回孟士墓」、裏に「姓吉田氏称寅次郎 安政六年己未十月二十七日 於江戸歿 享年三十歳」と刻まれている。百ヶ日忌に遺髪を埋めて建てたものである。 |
高杉晋作(東行)の墓 | |
 |
 |
|
| 松陰誕生地と萩の眺望 この地は一名「団子岩」ともいわれ、幼児期を過ごした所です。 |
吉田松陰先生銅像 この銅像は、明治維新100周年を記念して、1968(昭和43)年に建立されたものである。松陰先生が弟子の金子重輔を従え、下田沖のペリー艦隊を見つめている姿を彫刻したもので、高さは約8mある。題字は、同時の佐藤栄作首相が書き、銅像は萩出身の日展審査員長嶺武四郎が製作している。 |
|
 |
 |
 |
玉木文之進の墓 |
久坂玄瑞の墓 |
|
昼食は、城下町に行き、日本料理の「あじろ」ってお店へ。店員さんの愛想はあんまり良くなかったけど、器も料理も良かったよ。
| 「あじろ」のあじろ御膳 刺身、野菜煮物、煮魚 |
|
| その後、萩焼体験まで時間があるから、城下町散策をしようかと思ったけど、駐車場が見当たらず、俺だけ残して、両親は萩焼へ。近くの中央公園に駐車場があったんだけど。もっと下調べしておけば、良かったかな。 で、まずは、菊屋住宅へ。若い女の子の観光客が多かった。とはいうものの日帰りツアーなのか、時間になると、観光バスに戻っていきましたが。そこから、城下町地区を散策。次は、高杉の生家へ。続いて円政寺へ。高杉や伊藤が遊んだお寺なんだけど、神仏分離がされていなく金比羅社も一緒にある。高杉をびびらせた天狗の面や十二支が一周している社殿とか、やたら商業主義のにおいがするけど、住職なのかな、おじいさんの話が面白かった。この町の一角から、何人もの総理大臣が出たとか、東大卒が多いとか、郷土自慢が続いてね。話は面白かったんだけど、庭先なので、蚊が多かったのには、参ったな。 次は、青木周弼宅。周弼の弟が、研蔵。その養子が周蔵で、曾孫にペルー大使公邸占拠事件の青木盛久。と有名人一族。羽織袴のお姉さんが受付でお留守番していたけど、一緒に写真を撮ってもらうように頼めず、残念。 さらに、木戸孝允の生家へ。午前中の松下村塾、玉木邸、伊藤邸など、萩の武家屋敷に食傷気味。まっ、一通り見学したって感じかな。 (右)このあたりの地図 |
 |
| 菊屋住宅 |  |
 |
 |
 |
有栖川宮熾仁親王(1833-1895 明治維新のとき東征軍大総督、のち兵部卿、参謀総長などを歴任)が、1890(明治23)年6月22日に萩に来た際、菊屋剛十郎宅に3泊した際の食器類。萩焼は、九代坂高麗左衛門の作である。 |
 |
柱時計 伊藤博文の初洋行した際のアメリカ土産。 アメリカコネチカット州(ニューイングランド地方)セット・トーマス社製。時計内部の説明文が、現在のアメリカでは余り使われない古文体の英語で書かれている。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
(上)ふすまが奥まで閉まらないように、さんの切れ目が途中までしかない工夫がされています。 |
 |
 |
田中義一(1863-1929)生家跡 幕末ごろ御六尺(かごかき)田中家の三男として1863(文久3)年、乙熊がここで生まれた。乙熊は3歳の時、平安古に移り、成長して義一と名を改めた。13歳の時に新堀小学校の受業生(代用教員)に登用され、萩の乱にも参加したが、のち陸大に進学した。1918(大正7)年以降、陸軍大臣、次いで大将に進み、再び陸軍大臣となる。1925(大正14)年、政友会総裁に就任、1927(昭和2)年、内閣総理大臣となり外務大臣、拓務大臣をも兼任した。 |
| 高杉晋作誕生の地 幕末に活躍した高杉晋作は、1839(天保10)年、萩藩士高杉小忠太の長男としてこの地に生まれた。この旧宅は、家禄200石を受けていた、父小忠太宅で、現存する当時の建物は、座敷(6畳床間付)次の間(6畳)居間に(6畳、4.5畳)小室に(3畳)のほかに、玄関、台所がある。土蔵、納屋もあったが、現存していない。庭園に鎮守、裏庭には井戸がそのまま残っている。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 金比羅社圓政寺 圓政寺(真言宗)の入口に玄武岩の鳥居が建っているのは、境内に金比羅社があるからで、神仏混淆の名残である。 |
||
 |
 |
円政寺内金比羅社社殿 金比羅社の建立年は不詳であるが、入口に金比羅社に寄進された鳥居が建っており、それに1745(延享2)年と彫られている点や天保年間(1830~43)に編纂された「八江萩名所図画」に現在の社そのままの姿が描かれていることなどから、少なくともそのころには建立されていたと思われる。 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
| 拝殿前に一対の萩藩鋳物師制作の銅製狛犬が置いてあったが、戦時中供出せられ、現在は1960(昭和35)年に造られたのが据えてある。その台石は高彫の見事なものであり、当時の萩の名工の遺作である。 境内にある金比羅社は特異な建物で、軒下欄間に十二支の彫刻がめぐらしてあるが、同社にまつわる話題としては次の二つが有名である。 (1)1815(文化12)年12月11日、城下東郊香川津に住んでいた坪井甚右衛門組下の御六尺(藩公の駕籠かき)長七の長男権蔵と三男利吉の二人が、母の産後の病気治癒を祈願し、七日七夜断食し金比羅社に詣り、満願の夜丸裸で雪の中を家に帰る途中、松本川東岸の雁島付近で凍死した事件である。これは当時から「香川津の二孝子の美談」として語り伝えられた話で、藩公の名により山門内側に頌徳碑が建てられている。 (2)金比羅社の拝殿の前に大きな赤い天狗の面がかけてあるが、天保の末年、近所に生まれた高杉晋作がまだ幼かったころ、家人に、いつもここに連れてこられて、この面を見せられて、もの恐れしないようにしつけられたという。 ここで見るべきものとしては、1699(元禄12)年8月、萩藩の鋳物師郡司権助正信鋳造の半鐘が本堂拝殿にある。 |
||
 |
この神馬は、1820(文政3)年、萩市浜崎町の金子音松が、金比羅社に奉納したもので、山口市大内の名工安永貞右衛門の作である。高杉晋作や伊藤博文は子どもの頃、この境内が遊び場であり、いつもここに来ては、馬の鼻をなでていたという話である。 | |
 |
(左)大燈籠 (右)円政寺 |
 |
| 青木周弼旧宅 この家は、藩医(西洋内科)で蘭学者であった青木周弼の旧宅である。1859(安政6)年に建てられたものであるが、あまり改造されておらず、当時の様子をよく残している。 |
 |
 |
| 木戸孝允生家 (下)木戸孝允 幼年時代の手習い『今日』 |
 |
 |
 |
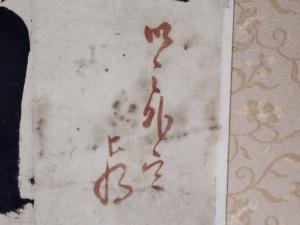 |
お城まで行くぞって気合いを入れ直し、歩き出す。バスを使おうとか、計画的に回ろうと考えず、かなり無謀だったったんだけど、田中義一の忠魂碑を見て、旧児玉家の長屋門、旧梨羽家書院、旧祖式家長屋、旧明倫館跡を通り、堀内鍵曲へ。武家町の風情が残っている一方で、土塀だけが残り、中は荒れ放題の売り地になっている現状も事実。文久2年に政庁が山口に移り、忘れられ取り残された町としての萩って一面もあるんだろうなぁ。
| 忠魂碑 陸軍大将男爵田中義一書 |
 |
|
| 旧児玉家長屋門 |  |
|
| 旧梨羽家書院 梨羽家は萩藩大組(683石余)の藩士で、屋敷は堀内地区の重臣たちの屋敷街に位置していた。敷地面積から考えても他の数棟の建物があったと思われるが、現在はこの書院しか残っていない。 |
 |
|
| 旧祖式家長屋 祖式家は、宇部市棯小野に領地を持っていた武士で、主計頭就好は、初代萩藩主に側近として仕えた。 |
 |
|
| 旧明倫館跡 ここは萩城三の丸の南、平安古ノ総門の北西100mの所にあった藩校跡で、全敷地940坪の広さがあった。1719(享保4)年5代藩主毛利吉元によって創建され1849(嘉永2)、城下の中央江向に移され再建されるまで130年間にわたって防長二州における最高学府であった。江戸時代200余りあった藩校のうち、12番目に出来、設備、教育内容ともに全国有数のものであった。 |
 |
|
| 堀内鍵曲 「鍵曲」は、敵の侵入や攻撃に備えるため、左右が高い土塀で囲まれた、見通しのきかない鍵手形の道路である。 |
 |
 |
 |
 |
|
ようやく、口羽家住宅にたどりつき、さらに旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、萩資料館を見て、萩城趾へ。
| 口羽家住宅 口羽家は、萩藩の寄組士(1018石余)で代々萩城三の丸に住んだ。大身の武士の住居地区であった堀内地区に現在も旧藩時代そのままの姿をとどめている。 |
相の間(あいのま) 二つの部屋の間にある小部屋で、表と内を分け隔てる緩衝帯としての役割を持っており、また、武者隠しの名残をとどめているとも思われる。これは、主人の身辺を警護するために家来が身を隠していた場所であり、萩市内に現存する武家屋敷中、こうしたものが残っているのは非常に珍しいものである。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
天樹院 萩開府毛利輝元の墓所で、輝元と夫人および、殉死者長井次郎左衛門の墓石三基がある。ここは、以前、輝元の本邸があったところで、彼の没後に天樹院(輝元の法号)が菩提寺として建てられたが、1869(明治2)年に廃寺になり墓所のみが残っている。 |
 |
旧厚狭毛利家萩屋敷長屋 厚狭毛利家は、毛利氏の一門で厚狭(現 山陽町)に知行地を持っていたため、このように呼ばれた。この長屋は、棟札による、1856(安政3)年に建てられたものである。桁行51.5m、梁間5mの長大な構造で、現在萩に残っている武家屋敷では最も大きいものである。 |
| 萩城趾 関ヶ原の合戦の敗戦で、西軍の総大将であった毛利輝元は、長門・周防2国に移封された。輝元は、1604(慶長9)年、日本海に面した長門国の萩に築城を開始し、阿武川河口の三角州を整地した。萩城は、標高143mの指月山の山麓には本丸が築かれたことから指月城とも呼ばれる。城郭の構造は、指月山麓の平城の部分と山頂の山城の部分を合わせた平山城の形式で、山麓には本丸・二の丸・三の丸を備えていた。本丸は、東西110間、南北80間、その南北には内堀を掘りめぐらし、高さ6間の石垣を築いて五層の天守閣がそびえ、内部には藩主の居館や成長などが立ち並んでいた。内堀に接してその外に二の丸があり、さらに中堀を挟んで広大な三の丸が城下町と外堀を隔ててつくられていた。城跡は指月公園となり、壮大な本丸の石垣や天守閣跡が往時を偲ばせる。 |
 |
|
 |
 |
天守閣跡 本丸の南西にあたる位置に高さ14.4m、下層は東西19.8m南北16.2mの5層の天守閣があった。最上階は、高欄にめぐらした桃山初期の形式を示す白亜のもので、初層が石垣の外に張り出した俯射装置として利用できるようになっていた。 |
 |
 |
|
| 旧福原家書院 福原家は、厚狭郡宇部に給領地(11314石余)を持つ萩藩の永代家老であった。この建物は、三の丸(堀内)にあった萩屋敷内の書院で、1882(明治15)年に現在地に移築した。 |
 |
|
 |
志都岐山神社 1878(明治121)年に、旧本丸付近に、萩の有志が山口にある豊栄、野田両神社の分社として建てたものである。主神は、毛利元就、隆元、輝元、敬親、元徳の5本柱、その他に初代から12代までの萩藩主が祀られている。 |
|
| 梨羽家茶室(煤払いの茶室) 東郊(東方の郊外)中津江にあった寄組士梨羽家(3300石)の別邸茶室で、城内煤払いの際、藩主が一時居城を出てここに休んだことからこの名がある。全国的にもまれな花月楼形式の優れた茶室である。 |
 |
|
 |
 |
指月山 指月山は、日本海中の独立山で、本土との間に出来た砂嘴によってつながれた陸繋島です。山体は花崗岩で出来ていて、海抜143m。防長二州に封ぜられた毛利氏はこの山を埋め立てて築城し、1608(慶長13)年に完成したが、この時から約260年間にわたる藩政時代を通じて、その森林は城内林として保護され、そのまま維持され、今日に至っている。そのため山体を覆う森林はよくその姿をとどめ、温暖帯照葉樹林として日本でもまれに見る成熟した森林である。これらの樹木は周囲6.4mもあるクスノキをはじめ、シイ、ツバキ、イスノキなどの常緑広葉樹に多少の落葉樹が混生している。その他サザンカの群生が見られ、その自生北限地となっている。指月山は、国の天然記念物に指定されている。 |
| 花江茶亭 この建物は、安政の初め(1854年ごろ)萩藩13代藩主毛利敬親が花江御殿(川手御殿、常磐江御殿)内に造った茶室である。幕末の多事多難の折、この茶室で敬親は支藩主や家臣たちと茶事に託して、格式を捨てて時勢を論じ国事を画策したといわれる。 |
 |
|
 |
(右)潮入門跡 (左)二の丸土塀(銃丸土塀) (2013年8月24日撮影) |
 |
よしっ、宿に戻るぞってガイドブックを見ると、循環バスと逆回りに歩いていたと気づく。結局、歩くしかないってことで、旧周布家長屋門、旧繁沢家長屋門、旧益田家物見櫓。北の総門を通る。そこで、お母さんから萩焼体験が終わったからって、お迎えメール。しかし、お互いの位置関係が上手く伝わらず、野山獄、岩倉獄まで歩いてしまう。まっ、その直後に拾ってもらって、宿に戻れました。
ホントに、11日丸一日かけた萩観光は、充実していた。半分意地で回っていたかもしれないけど。
| ★本日のお宿「萩本陣」の夕食 食前酒 梅サワー |
   |
   |
|
   |
![]()
12日は、萩から津和野、そして山口へ。朝、萩焼会館で買い物をしてから国道191号で、海沿いを須佐経由で行ったけど、海に出ないで山越えで行った方が近かったみたい。
津和野では、乙女峠のマリア聖堂を見て、殿町通りを散策。「沙羅の木」で昭和50年生まれのコーヒーゼリーを食べたり、名物のうずめめし定食を「能濃」で食べたりした。森鴎外や西周の旧宅や、太鼓谷稲成神社とかの見所に行ってないのもあるけど、そんなのよりも興奮したのは、SL。津和野は、お母さんが行きたがっていたので、俺に気をつかってくれて津和野から山口の湯田温泉まで、SLを予約してくれた。「沙羅の木」の売店で、1時頃にSLが来るって耳にして、駅へ。SLを見たことがないわけじゃないけど、やっぱり興奮する。走ってきたSLに感動したけど、それ以上にすごかったのは、ターンテーブル。ぱっと見では、何の施設だかわからなかったけど、機関車1台分のレールが回転台にあったり、待機中に煙をまき散らさないように吸塵装置があったり、装備に興奮。
3時頃、また駅に戻り、乗車。2号車は、オリエント急行風の車両で、豪華さに感動。出発してから車内探検。何度も出たり入ったりして、隣の席の方には、迷惑をかけただろうな。1号車の展望車両では、写真を撮ってもらうときに、隣の女の子の家族と間違えられたりしたけど、1号車から5号車まで見て回ったり、先回りした両親に山口駅で待ち合わせしたり、充実していたね。
| キリシタン殉教史跡 乙女峠マリア聖堂 この乙女峠には、明治初年まで光琳寺という寺があった。1868(明治元)年から1873(明治6)年まで153人の長崎浦上のカトリック信者が、信仰のためにこの寺に収容された。彼らは、戦国時代の信者の子孫であり、その信仰を密かに守っていた。全国各地へお預けの身になった者のうち、津和野に流された彼らは、4年の間信仰を改めるようにとここで筆舌に尽くせぬ辛酸をなめさせられた。そのうち、ついに54人は棄教した。信仰を忠実に守り通した信者なかには、困難な生活と残酷な拷問のために、殉教の死を遂げた者が36人いた。彼らのうちの1人安太郎は三尺牢に入れられ、そこで聖母マリアの出現を賜って死の前に励まされた。1873年(明治6)には、宗教の自由が宣告され生き残った者は長崎に帰った。 |
||
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 津和野市街 |  |
 |
 |
家老多胡家表門 多胡家は、津和野藩の筆頭家老職を藩主亀井家11代にわたり務めた。 多胡家に関わる銘菓物語(源氏巻) 1698(元禄11)年、赤穂の浅野内匠頭の刃傷が起こる前、当時の津和野藩主、亀井滋親が勅使接待役を命じられ、吉良上野介に典儀故例の指導を受けていたが、浅野同様、数々の辱めを受け大いに憤り、吉良を斬って自らも自害する決意をした。それを知った国家老多胡外記が、御家の一大事と早速吉良家に進物を送りつけたところ、吉良の態度は一変、殿様は無事大役を果たすことが出来た。そのときに進物「小判を包んだ形のお菓子」が源氏巻の原型となった。津和野を救った縁起の良いお菓子で、地元の方々にも大変親しまれている銘菓である。 |
|
| (中)大岡家老門 (右)津和野町役場津和野庁舎 |
 |
 |
 |
カトリック教会 この聖堂は、神のより大いなる栄光と乙女峠36人の殉教者の遺徳を偲び讃えるため、1931年に建てられた。長崎・西坂の日本26聖人殉教者の保護のもとにおります。 |
|
| 珈琲ゼリー(沙羅の木オリジナル) 昭和50年より変わらぬおいしさ |
 |
 |
 |
 |
 |
「能濃」の名物うずめめし定食 |
 |
 |
| 駅のそばに展示されていた D51型蒸気機関車 日本の代表的蒸気機関車“デゴイチ”は、我が国の機関車発展史上の最盛期にふさわしく国鉄の総合技術の粋を集約し、D50型の近代化改良型として1936(昭和11)年3月に1号機が生まれた。以来、輸送量の増加に対応するためD51の新製車が全国の工場で製作され、1946(昭和21)年1月までに実に1115両の最大両数を記録している。 |
 |
 |
 |
 |
|
| 実際に乗ったC51 1の車歴 機関車番号 C51 1 1937(昭和12)年から201両製造された旅客用蒸気機関車。C55型を改良して誕生した機関車。細いボイラーと大きな動輪の組み合わせからスタイル全体のバランスがとれ、「貴婦人」の愛称で親しまれてきました。 |
 |
 |
| ターンテーブル 新山口駅方面から来たSLやまぐち号は、留置線に客車を留置したのちに、機関車のみ、方向転換のため、転車台(ターンテーブル)に向かう。転車台に乗って、反時計回りに回っている様子がわかりますか? |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 吸塵装置 待機中に煙をまき散らさないように吸塵装置が設置されている。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 津和野駅から、さぁ出発! |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
1号車
「展望風車輌」(下3枚) 赤と金の織りなす紋章風のゆったりとしたソファ調の座席、網棚とは思えないベルサイユ調の華麗な飾り棚や、花柄のカーテン、気品のあるおだやかな灯をはなつルームライト。旅のひとときを世俗を離れ家族的で優雅な雰囲気を充分に味あわせてくれるインテリア。 |
 |
 |
 |
| 2号車 「欧風車輌」 この車輌は、オリエント急行をモデルにした欧風車輌。 |
 |
 |
 |
3号車「昭和風車輌」 昭和2年から7年まで続く慢性的経済恐慌の状態、そして廃線を体験した激増の時代があった。 |
|
| 4号車「明治風車輌」 「明治維新による開国と統一の時代」 |
 |
|
 |
5号車「大正風車輌」 大正時代は、明治の国民国家建設と昭和の戦乱の時代とにはさまれた、ほんのひとときの「夢見る大衆」の時代でした。生活にゆとりが出てきた人々は、町に群がり市外電車は鈴なりでした。市場や百貨店では、機能的で垢抜けたデザインの文化機器が大いに売り出され夢見る老若男女は活動写真に殺到した。そういう時代の特色を反映してか、この車輌は明治時代と比べて10数センチも座席が高くなり、色も華やかなうぐいす色になり全体的に明るい雰囲気につくられている。 |
|
| ★本日のお宿「ホテル松政」の夕食 先 附 三種 |
    |
    |
|
    |
![]()
最終日。今朝、両親と別れ、一人旅復活。9:02湯田温泉駅発のスーパーおき2号で、大田市まで。新幹線よりも揺れる。ネットで検索したら、電車ではなく気動車(ディーゼル車)のうえ、高速でカーブを通過できる振り子式車両ってことで、揺れて当然だよね。津和野、益田、浜田、江津、温泉津、馬路、仁万など、これまで通ってきた地名を戻り、大田市に着いたのは11:44。湯田温泉駅で、お母さんに買ってもらったおにぎりを車中で食べ、昼食に。路線バスで、世界遺産センターへ。
| ★本日のお宿「ホテル松政」の夕食 |   |
|
| スーパーおき2号 |  |
 |
10日に行ったときはガラガラだった石見銀山の駐車場も、センターの第三駐車場まで満車で、県道31号まで行列。想像してた混雑で、ちょっとホッとしたりして。ツアーも、当日申し込みができないほど満員だったけど、名簿を見たら、俺が一番早く申し込んでいた。やる気があるねぇ。手違いで、受付ミスなんてのもあったけど、無事参加できました。
ガイドのおじさんが、まずは概略説明。ホントに、わかりにくい世界遺産ってことで、事前学習が大切。クロアチアのプリトヴィッチェ国立公園なんて、事前知識まったくなしでも、感動ものだったけど。
それから、バスに乗って本谷地区へ。番所跡、下金生坑、金生坑を通って、大久保間歩に着く頃には、汗だくに。そういえば、江戸時代までに開発されたのを間歩って呼んで、明治以降が坑なんだって。確かに、人力と機械堀の違いもあるからね。汗だくで、めちゃめちゃ暑い体にひんやりとした冷気が。そこが大久保間歩でした。中の冷気が流れ出てるんだよね。管理小屋でヘルメットと長靴と懐中電灯を借りる。衛生面の配慮で、シャワーキャップと使い捨ての中敷きも渡される。案内文とかにも書いてあったけど、何を大げさなって感じだけど、本当に必需品。間歩の中は水たまり状態で、長靴でジャブジャブ歩く。照明設備がないから、懐中電灯が唯一の光源。インディージョーンズのテーマを歌い出す子どもがいたけど、ホントにそんな感じ。銀の鉱脈、江戸と明治の違い、小さい分かれ道など、あるものは龍源寺間歩と大差ないけど、規模が違いすぎる。龍源寺間歩も、ガイドブックで読んだイメージ以上の規模でビックリしたけど、大久保間歩は制限時間の30分じゃ全然足らないよぉって感じの大きさ。本当にすごかったし、わざわざ石見銀山に戻ってきたかいがあった。
大久保間歩から、さらに上へ行って、釜屋間歩へ。安川伝兵衛が江戸初期に発見した大規模の間歩。さらに、階段状の岩の遺構が発掘されるなど、見所満載の間歩でした。
ガイドさんの話で印象に残ったのは、まだまだ遺構がいっぱい埋まっているのはわかっているけど、発掘してしまうと、保存するためにはお金がかかる。それ以前に、発掘にもお金がかかるってことで、放置状態になっているって話。加茂岩倉も、荒神谷も、農道を開発する途中で見つかってしまったわけで、土地の所有者が調査費用を負担しないといけないから、見つかってもつぶしてしまうこともあるんだろうな。そんな中で、開発と観光と保存を両立させていくのは、難しいんだろうな。石見銀山って世界遺産を今後どうしていくのかは、大きな課題だろうな。
バスを待っている間に、雨が降ってきたり、最後の最後でトラブルになったけど、大田市から出雲市まで移動して、出雲そばを食べて夜行バスへ。全然、調べてなかったけど、同じ時間に出雲市駅から寝台特急も出てたんだね。金額が高いけど、久しぶりに寝台車に乗るのも良かったかな。とはいえ、予定通りに夜行バスへ。ガラガラのバスで、隣の座席まで使って横になれた。予定より早く新宿に着いて、立川に帰ってきました。

![]()