2012年9月22日(土)23日(日)の1泊2日で、姫路城、三徳山三佛寺投入堂など、国宝ツアーに行ってきました。
普段は、一人旅が多い私ですが、今回の旅行は、仲間がいました。いつものワイン会のメンバーで飲んでいるときに、「姫路城が、修理工事中で、外から見られるらしいよ」「鳥取の投入堂に行ってみたいな」なんて、話しているうちに、行くことになりました。一緒に感動できる体験って、素晴らしいですよね。
・姫路城(大天守修理見学施設「天空の白鷺」)
・蒜山ワイナリー
・三朝温泉
・三徳山三佛寺
・倉吉
・鳥取砂丘
| 姫路城大天守は、2009年(平成21年)から、漆喰壁の塗り直しや屋根瓦の吹き直しを中心に、約5年間かけて行なう保存修理工事が行なわれている。工事中は、天守内部の見学はできないが、工事のための素屋根に、見学スペース「天空の白鷺」を設け、工事中の大天守の大屋根及び最上層を外側から間近にみることができる。 |  |
 |
| リの一渡櫓 これまで一般公開されたことのない「櫓」が、保存修理期間中に限り、特別公開されていました。リの一渡櫓は、二重二階の櫓で、初層の東北面に土庇が付属している。 |
|||
| 大天守の鯱 瓦葺屋根の大棟の両端につけられる飾りの一種で、鬼瓦と同様に建物の守り神とされた。姿は魚で頭は虎、尾鰭は常に上を向き、背中には幾重もの鋭いとげを持っているという想像上の動物を模している。 |
 |
 |
 |
| 姫路城大天守の鯱、三代目と考えられ、鯱の取り替えの際に、江戸期から城主とつながりのある圓教寺が城主から拝領し、大切に保管してきたものである。 銘文には、1803(享和3)年制作と記されており、現存する大天守の鯱としては最古のものと考えられる。 |
昭和の大修理の際に、大天守の東側に上がっていたものである。全国的な傾向として江戸中期以降の鯱は耐久性に乏しいため、新しい鯱と入れ替えた。 銘文には1910(明治43)年制作と記されている。 |
昭和の大修理の際に、大天守の三層の屋根「大千鳥破風棟」に、1687(貞享4)年の銘がある二代目と考えられる小型の鯱が発見され、大天守の11尾の鯱がこれをもとに復元された。 | |
 |
 |
 |
| 「天空の白鷺」内のエレベーター。これに乗って、8階まで、レッツゴー。 | 立体的な揚羽蝶の鬼瓦は、隅棟に据え付けられていた。五重の他二重の隅棟にも据えられていて、同じ文様の鬼瓦は8面ある。揚羽蝶紋は、池田氏の家紋である。 | 平面的な揚羽蝶の鬼瓦は、築城当時のものである。 |
 |
 |
 |
| 葺き替えられた屋根。屋根瓦の継ぎ目に漆喰を塗る「屋根目地漆喰」は、姫路城、熊本城、松山城、明石城など、使用されている城は数少ない。 | 上層部(4・5層)は土壁まで取り除き、下地から修理される。下層部(1~3層)は、表面の漆喰を塗り替える。写真は、最上層の外壁で、土壁の芯となる「小舞」に土がつけられた状態である。この後、漆喰が塗られていく。 | |
| 播州姫路本町 たまごや 玉子かけご飯専門店。カツオ節と薬味に、特製のだし醤油をかけ、シンプルにいただく。玉子、ご飯ともに、おかわり自由。穴子やカマンベールチーズなど、トッピングも可。 なんとご飯と卵が、おかわり自由。おいしいお米と卵があれば、いくらでも食べられるかと思いましたが、1回おかわりしただけでした。もったいなかったかな? |
 |

 |
 |
三朝温泉街 |
 |
 |
恋谷橋・かじか蛙 この橋にあるかじか蛙像は、縁結びのかじか蛙として親しまれており、撫でることでご縁を授かることが出来ます。 |
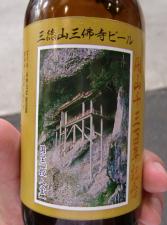 |
三徳山三佛寺地ビール ちょっと濃いめの美味しいビールでした。このビールを片手に、三朝の温泉街を散歩しました。 |
 |
「ブランナールみささ」の夕食 町営の国民宿舎のため、安い料金でしたが、こんなに豪華な夕食でした。 |
朝、起きたら、外は雨。「このまま降ってたら、投入堂には行けないかな」、「他の予定はなしにして、行けるまで待ってみようかな」なんて、いろいろ考えてしまいましたが、出かける時間には、雨は上がり、フロントの方が、電話で確認してくれたら、「大丈夫」ということで、出発。
投入堂までの道のりは、大変なのはわかっていたけど、鎖を使って岩登り程度かと、結果として、甘く見ていました。でも、自分の中では、最大級の危険さを想像していたんだけど…。結果は、想像を絶する危険さ。命の危険まで感じちゃいました。あんなところを一般開放していいのって感じ。木の根のへばりついて体を持ち上げたり、足場を探りながら岩にへばりついたり、鎖を登ったり。ちょっとでもミスったら、死ぬんだろうなぁって緊張感。途中で、リタイアした人もいましたが、それが正解。「最後まで、頑張ろうよ」と言ったものの何かあったら、責任取れないもんな。
でも、その分、たどり着いたときの達成感は、ものすごかった。充実感がありまくり。帰りは、行く人に声をかけアドバイス。同じ困難に立ちむかう戦友って感じ。他人に優しく親切になれる場所だったな。
三徳山三佛寺は、土門拳の『古寺巡礼』でも、紹介されている。
「日本第一の名建築は何かと問われれば、私は躊躇なく三仏寺投入堂を真先に挙げる。」
「投入堂は本当に美しい。その建築美は日本一だ。しかしまた撮影の必要が起これば兎に角、三徳山の険阻艱難を思うと、二度と行きたいとは思わない。」
2ヵ所抜粋したが、投入堂の美しさと、そこに行くまでの困難が十分伝わると思う。
<2019年12月30日追記>
網野善彦『日本中世の民衆像-平民と職人-』(岩波新書(黄版)136 1980年)で、「伯耆国美徳山領温谷別所検注目録」『壬生家文書』が紹介されています。
「美徳山は伯耆国の大山などとならぶ著名な大寺院で、修験などとも関わりが深い有名な寺院ですが、この文書は、その別所に付属している田地の一三四四年(康永三)の検注目録で、田地を一筆ごとに検注して取帳をつくったのちに、それをまとめ、整理した目録であります。」と説明され、「田地に木製の蓋物である合子が賦課された」例として紹介されています。
| 三徳山入峰修行(投入堂参拝登山)心得 三徳山は修行の場であり、木の根や岩やクサリをよじ登る等、場所によっては険しい箇所がございます。 ●参拝受付時間は8時から15時まで。入山手続き下山手続きを必ず行ってください。 |
| 近年、投入堂参拝者の観光気分、観光装備による滑落事故が多発しています。厳しい修行の道であると理解の上、受付ください |
 |
 |
駐車場から、県道を歩いて、正面階段(上左・上右)へ。参拝者受付案内所で、400円払い、本堂へ。その裏の登山参拝事務所(中左)で、200円払うのですが、そこでは、靴の底のチェックがありました。滑りやすい靴やヒールなどで来ると、登山できないか、わらじを買うことになります。 修行ですので、輪袈裟(中右)を借りて、修行登山スタートです。 入口の門(下左)をくぐると、宿入橋(下中)があります。まだまだ、余裕な私は、先を歩く仲間を写真に撮っていますね(下右)。 「六根清浄」 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 最初の難所かずら坂。むき出しの木の根に、両手、両足をかけ、体全体でへばりつく。足を掛ける場所が見つからないときは、腕力で体を持ち上げる。ここも、登山道らしいけど、少なくとも、「道」ではない。 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| かずら坂を越えると、文殊堂が見えてきます。その前に次の難所くさり坂が登場。岩にくっついて登っていくと、文殊堂の真下に出ます。文殊堂は、清水の舞台のように、「懸造」の技法※で建てられているので、写真だけ見ると、清水の舞台の写真のようですね。その文殊堂の真下から、クサリを使って、岩登り。やっとの事でたどり着いた文殊堂からの眺めは、すばらしいものでしたが、写真の通り、縁側には柵がない、それどころか、雨水がたまらないようにと外に向かって傾いています。足を投げ出して座って休憩しても、気持ちはなかなか落ちつきませんでした。
|
||
 |
 |
文殊堂から、地蔵堂へ。さらに、鐘楼堂で鐘撞き。でも、こんな所まで、どうやって鐘を持ってきたのだろう?私の考えでは、 ①この場で、鋳造した。 ②宇宙人がUFOで運んでくれた。 のどちらかだと思うのですが、たぶん、何かの方法で運んできたんでしょうね。 さらに、馬の背、牛の背と呼ばれる岩場を通っていきました。かなり危ないのですが、これまでのコースに比べたらねぇ。 |
 |
 |
 |
| 左から、納経堂、観音堂、元結掛堂。どれも、岩のくぼみに建てられています。特に、納経堂は、現存する神社建築としては、投入堂と同じく日本最古級のもので、平安時代後期(12世紀)頃の建築とされています。 | ||
 |
 |
元結掛堂から、さらに先に歩いて行くと、山道が右に曲がります。すると、一気に視野が開け、投入堂の姿を見ることができます。 |
| 投入堂は、三徳山三佛寺の奥の院であり、修験道の本尊の金剛蔵王大権現を安置するお堂。日本でも代表的な懸造建築である。正式には、手前の建物を蔵王殿、奥の建物を愛染堂という。 堂全面は断崖で近づく道すらない垂直な崖に、浮かぶとも建つとも表現しがたい優美な姿をかもしだしている。近年の科学調査により、平安後期の作であるとされ、現存する神社建築では、日本最古級ともいわれる。 慶雲3(706)年、役行者※が、三徳山を訪れた時、ふもとで造ったお堂を法力をもって断崖絶壁の岩窟に投げ入れたといわれ、「投入堂」と人々は呼ぶようになったと伝わる。
|
||
| こんな看板を見ると、ちょっと…。 (中)途中にあった「滑落現場」 (右)下に下りたら、大雨が。そのため、入山禁止になってしまいました。 |
 |
 |
 |
 |
お山に登られない方には、県道の遙拝所から投入堂が拝めます。でも、遠いですよねぇ。こんなとこまで、行ったんですよ。 |
| 白壁倶楽部 鳥取県で最初に国の登録有形文化財に指定された旧国立第三銀行の洋館を利用したレストラン&カフェ。 ランチは、ガイドブックで見つけたちょっとおしゃれな白壁倶楽部で。混んでるお店で、結構待ちましたが、ハンバーグはおいしかったです。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ハンバーグランチ 粗挽きハンバーグ 赤ワインソース ポーチドエッグ添え |
|
| 倉吉の町 白壁と赤瓦の町、倉吉。風情のある町で、ゆっくり散歩できたら良かったですね。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 鳥取砂丘 鳥取砂丘は、2度目でしたが、やっぱり午後に行くと、足跡だらけで、イメージしている砂丘と、ちょっと違いますね。 |
 |
 |
 |
 |
 |